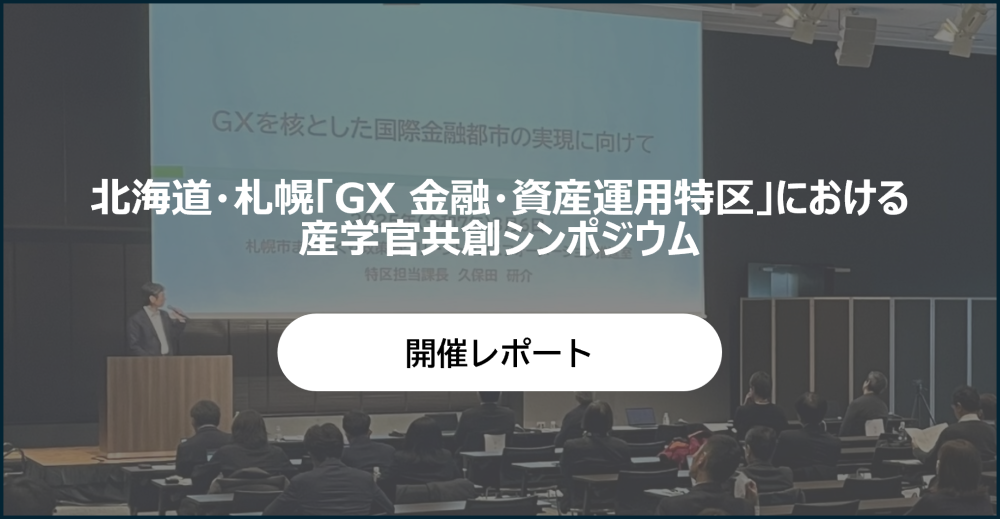
札幌・北海道では、GX投資の潜在力や自然と調和した街の魅力を活かし、「GX金融・資産運用特区」を活用しながら、GX産業のサプライチェーン構築・雇用創出を図るとともに、イノベーションを生み出すスタートアップの創出・育成を進め、資産運用会社等の金融機能を北海道・札幌に呼び込むべく取組を進めています。
また、次世代半導体・AI関連産業の集積やデータセンターの立地、水素サプライチェーンの構築など、我が国の経済安全保障にも貢献する様々な取組が進行しており、今後も多くの官民投資が期待されています。
こうした取組を更に加速させるためには、民間企業・大学・行政が地域戦略を共有し、それぞれが主体的に役割を果たしながら共創していくことが不可欠です。
本シンポジウムでは、産学官の主要プレーヤーが一堂に会し、産学官共創による地方創生を北海道・札幌で今後どのように進めていくかについて議論を行いました。
本レポートでは、その概要をお伝えいたします。
シンポジウム概要
- タイトル
- 北海道・札幌「GX 金融・資産運用特区」における産学官共創シンポジウム
- 主催
- 札幌市、株式会社日本総合研究所
- 開催
- 2025年3月6日(木)14:00~16:30
- 会場
- ベルサール新宿南口(東京都渋谷区)
プログラム
開会挨拶・趣旨説明
-

株式会社日本総合研究所 プリンシパル 東 博暢 氏 -
日本では「地方創生」が長年の課題とされ、特に消滅可能性都市の問題が深刻化している。少子高齢化や労働力不足、気候変動、経済安全保障などの課題を、新たな地域創生の機会と捉えるべき。従来、地域・国土政策と経済・産業政策は分断されがちだったが、近年では国交省と経産省の連携が進み、国内産業の回帰や地域と連携した産業振興の動きが加速している。
国際情勢の変化によりサプライチェーンが再編される中、国内では広域経済圏の形成が進み、DXやGXの推進が求められている。北海道は再生可能エネルギーを活かしたGX推進拠点として期待され、国家戦略特区の指定により規制緩和を活かした新産業の誘致が進む。社会構造の変革が不可欠であり、新たな成長モデルの構築を通じて、北海道が地方創生のモデルケースとなる可能性がある。
本セミナーでは、札幌市とともに産学官の関係者が議論を深め、今後の方向性を探りたい。
GXを核とした国際金融都市の実現に向けて
-

札幌市まちづくり政策局政策企画部
グリーントランスフォーメーション推進室特区担当課長 久保田 研介 氏 -
札幌・北海道は、国内随一の再エネポテンシャルや、都市と自然が調和した世界屈指の街の魅力を生かし、GX産業の集積と金融機能の強化集積を実現し、今後10年間で創出される150兆円超のGX官民投資のうち、40兆円を北海道・札幌に呼び込む目標を掲げている。道内では、洋上風力や次世代半導体、データセンターをはじめGXプロジェクトが進行している。
昨年6月には、金融・資産運用特区と国家戦略特区という2つの特区に指定され、これまでに銀行によるGX関連事業に対する出資規制の緩和や、海外企業の拠点開設手続の英語対応などの規制緩和を実現してきた。加えて、4月からはGX事業・金融事業に対する税制優遇制度もスタートさせる。
さらに、GX事業者や資産運用会社の誘致や、都心の再開発と連動した企業誘致の取組にも注力している。是非これからの札幌に注目いただきたい。
半導体産業の新潮流 ~産業構造転換による地方創生2.0
-

株式会社日本総合研究所
プリンシパル 浅川 秀之 氏 -
現在、半導体産業・AI関連産業の拠点形成はハードウェアのサプライチェーン構築が中心であり、九州・熊本ではTSMCを中心に工場建設が進んでいる。しかし、今後は半導体開発プロセスのデジタル化や、車載システム・AIチップなどソフトウェアの重要性が高まる。地方創生においても、ソフトウェアを軸とした拠点形成が鍵となる。
今後は工場中心の「求心力型」から、ソフトウェアを活用した「遠心力型」の拠点形成が重要となる。地理的な制約を超え、世界中から人材やノウハウを集めることで、地方創生の可能性が広がる。そのためには、国内の拠点選定を慎重に行い、熊本や北海道に限らずグローバルな視点で政策を進める必要がある。
北海道・札幌における産学官共創の現在
-

北海道大学 産学・地域協働推進機構 社会・地域創発本部 副本部長 齊藤 大地 氏
株式会社日本総合研究所 プリンシパル 東 博暢 氏 -
地方創生のためには、大学、企業、自治体が長期的な協力関係を築くことが不可欠であり、そのために研究支援体制の強化やURAの拡充が求められる。
国の政策として「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」が改定され、国際卓越大学や地域中核・特色ある研究大学が選定された。これまで以上に大学全体や地域を巻き込むことが必要だが、大学教員の研究時間減少が課題。産学官連携の推進にはURAやコーディネーターの役割が重要になっている。
北大では、J-PEAKSを通じて、道内大学とともに強みや特色を核として、産学官連携を促進するための体制の構築を開始。半導体分野では、北海道・札幌市・千歳市と連携しながら、地方大学・地域産業創生交付金を活用して取組を強化した。さらに、大学のリソースを一元化するため、本年1月に「総合イノベーション創発機構」を設置し、産学官連携や社会実装の加速を目指している。
パネルディスカッション「産学官共創による札幌の未来について」
-

(パネリスト)
- 株式会社三井住友銀行(SMBC) 公共・金融法人部 部長 松澤 尚史 氏
- キオクシア株式会社 先端技術研究所 研究戦略企画室 参事 吉水 康人 氏
- 地経学研究所 客員研究員 田上 英樹 氏
- 札幌市まちづくり政策局政策企画部グリーントランスフォーメーション推進室特区担当課長 久保田 研介
- 北海道大学 産学・地域協働推進機構 社会・地域創発本部 副本部長 齊藤 大地 氏
(ファシリテーター)
- 株式会社日本総合研究所 プリンシパル 東 博暢 氏
-
本トークセッションでは、「産学官共創による地方創生」「産業政策と地方創生の関係性」「今後の北海道・札幌への期待」という3つのテーマを軸に、半導体産業の発展や地域経済の未来について議論が交わされた。
地経学研究所の田上氏は、北海道に次世代半導体製造拠点ができることは世界的にも稀な機会であり、これを最大限に活用することが重要だと指摘。半導体のプロジェクトをテコに、産学官連携による取組の発展を期待したいと述べた。
SMBCの松澤氏は、札幌の魅力を活かすためには、民間企業が主体となるエコシステムの構築が必要だと指摘。行政主導から民間主導の成長モデルへシフトすることで、持続可能な発展が可能になると述べた。
キオクシアの吉水氏は、半導体の活用には出口戦略が重要であり、北海道の地域課題に焦点を当てた産業モデルの構築が必要だと述べた。ラピダスの進出を単なる製造拠点にとどめず、地域課題解決に貢献できるビジネスモデルを創出することが成功の鍵になると指摘した。
北海道大学の齊藤氏は、半導体分野では大学が国内外の企業と協力して人材育成プログラムを確立することが求められると述べた。また、北海道全体のスタートアップエコシステムの育成にも力を入れ、半導体産業と地域経済の融合を図ることが大学の新たな使命であるとした。
札幌市の久保田氏は、北海道が国家戦略特区に指定されたことを活かし、規制緩和を進めながら産業振興を支援する仕組みを作ることが必要だと述べた。特に、民間主導のプロジェクトを札幌市が後押しする形で進めることで、産学官金の連携をより強固なものにしていきたいと締めくくった。
シンポジウムを終えて
今回のトークセッションでは、北海道・札幌が持つ産業ポテンシャルと、それを活かすための産学官共創のあり方について多角的な視点から議論が行われました。特に、半導体産業を核とした成長戦略においては、人材育成・インフラ整備・資金調達・地域課題の解決が重要な要素として浮かび上がりました。
今後、民間主導のエコシステム構築や、規制緩和を活用した新産業の育成を通じて、札幌や北海道が国際的な技術拠点へと成長していくことがますます期待されます。
